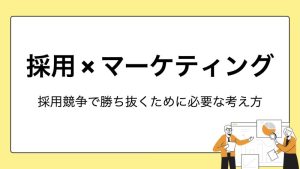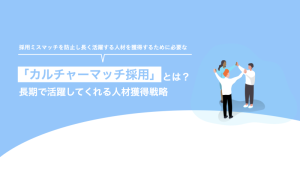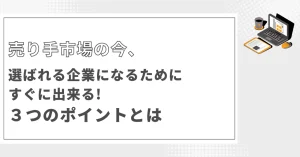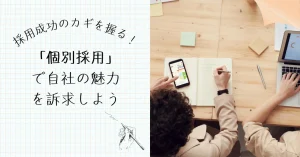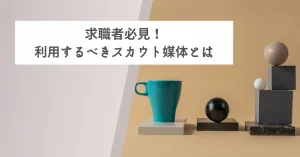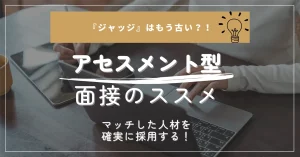採用マーケティングとは?今、採用にマーケ思考が必要な理由
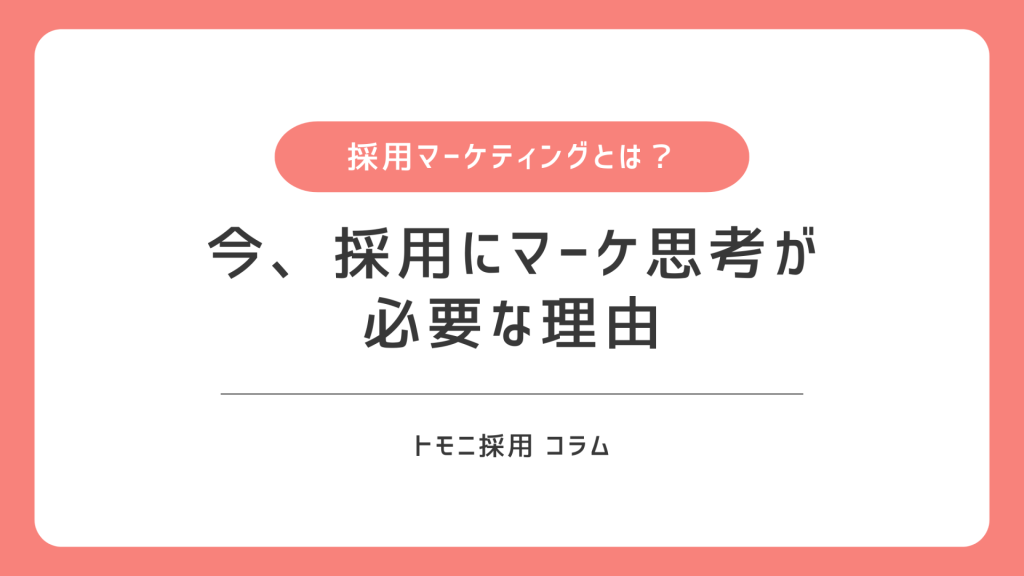
近年、採用市場は急速に“マーケティング化”しています。「求人を出していれば人が集まる」時代はすでに終わりを迎え、求職者の心を動かす“仕組み”を持つ企業だけが人材獲得競争を勝ち抜いています。
こうした背景の中で注目されているのが、「採用マーケティング」という考え方です。
これは、企業のサービスや商品を売る際に活用されてきたマーケティングの手法を、採用活動に応用するアプローチ。採用ターゲットの“行動”や“感情”を理解し、最適なタイミング・手法・コンテンツでアプローチする戦略です。
この記事では、採用マーケティングの基本概念から実践ステップまでを体系的に解説し、「選ばれる企業」になるための第一歩をお届けします。
採用マーケティングの定義と目的
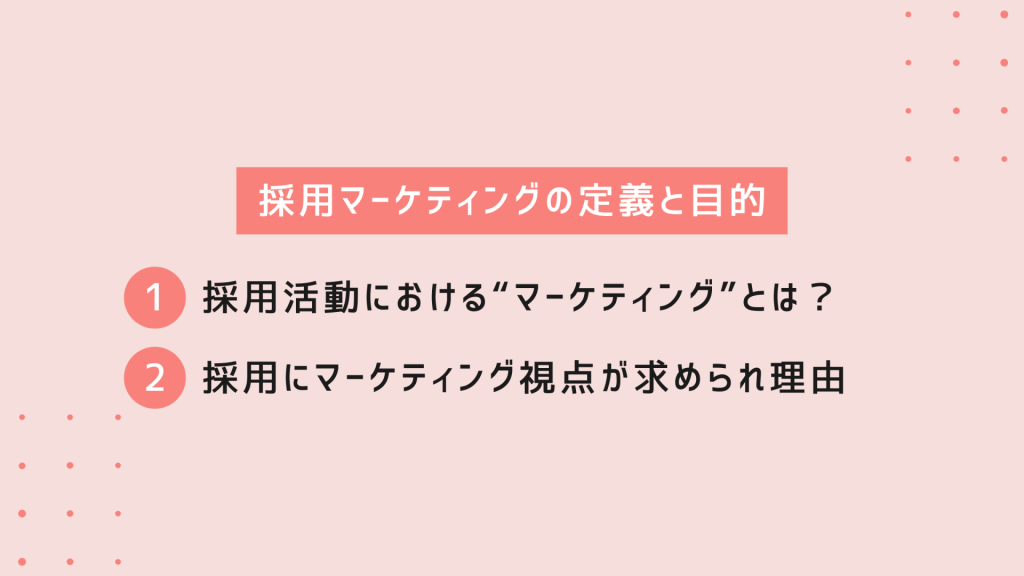
これまでの採用活動は、「人材を探す・待つ・選ぶ」という人事部門の業務の一環として行われてきました。しかし現代では、求職者側の情報収集力が高まり、採用競合も激化していることから、「いい人がいれば採用したい」という受け身の姿勢では成果につながりにくくなっています。
そこで注目されているのが、「採用マーケティング」という考え方です。
これは、企業が商品を売るために使ってきたマーケティング手法を採用活動に応用することで、「誰に」「どのように」「何を」届けるかを戦略的に設計するアプローチです。
この章では、採用マーケティングの具体的な定義や目的、そして従来の採用との違いについて解説していきます。
採用活動における“マーケティング”とは?
採用活動における「マーケティング」とは、求める人材に対して、企業の魅力や価値を適切なタイミング・手段で届け、応募につなげるための戦略的アプローチです。
従来の「求人を出して待つ」採用スタイルとは異なり、採用マーケティングでは、誰に・何を・どう伝えるかを設計し、応募前の接点づくりから入社までのプロセス全体を構築します。
たとえば、商品マーケティングでは「ターゲット顧客に向けた訴求」が不可欠ですが、採用も同様。職種・年齢・志向性に合わせて、ペルソナ設計やカスタマージャーニー(候補者の意思決定の流れ)を活用することで、より精度の高いアプローチが可能になります。
この視点を取り入れることで、以下のような効果が期待できます。
・自社にマッチした人材からの応募が増える
・応募者の理解・納得度が高まり、選考辞退や早期離職が減る
・再現性のある採用プロセスを構築できる
採用を“運”に頼らず、「選ばれる仕組み」として設計することが、これからの時代のスタンダードとなりつつあるのです。
なぜ今、採用にマーケティング視点が求められているのか?
近年、採用市場では「企業が人を選ぶ」から「人に選ばれる」時代へと大きくシフトしています。
優秀な人材は限られており、企業はただ求人を出すだけでは見つけてもらえず、ましてや選ばれることも困難です。こうした環境の変化により、採用にもマーケティング視点が不可欠となってきました。
その背景には、以下のような要因があります。
- 情報収集行動の変化
求職者は求人票だけでなく、SNS、口コミ、ストーリー記事、社員の発信などを通じて多面的に企業を調べています。採用広報や発信の「質」が応募を左右する時代です。 - 採用競合の増加と差別化の難しさ
同じターゲット層を狙う企業が乱立し、スキルだけでなく企業カルチャーやビジョンへの共感が意思決定に影響するようになっています。 - 採用コストの高騰
人材紹介手数料や広告費は年々上昇しており、より費用対効果の高い「仕組み化された採用活動」が求められています。
こうした中で、マーケティングのように「誰に」「どのように」届けるかを意識し、採用の入り口から入社後までのプロセスをデザインすることが、採用成功のカギを握ります。
採用マーケティングの基本フレームワーク
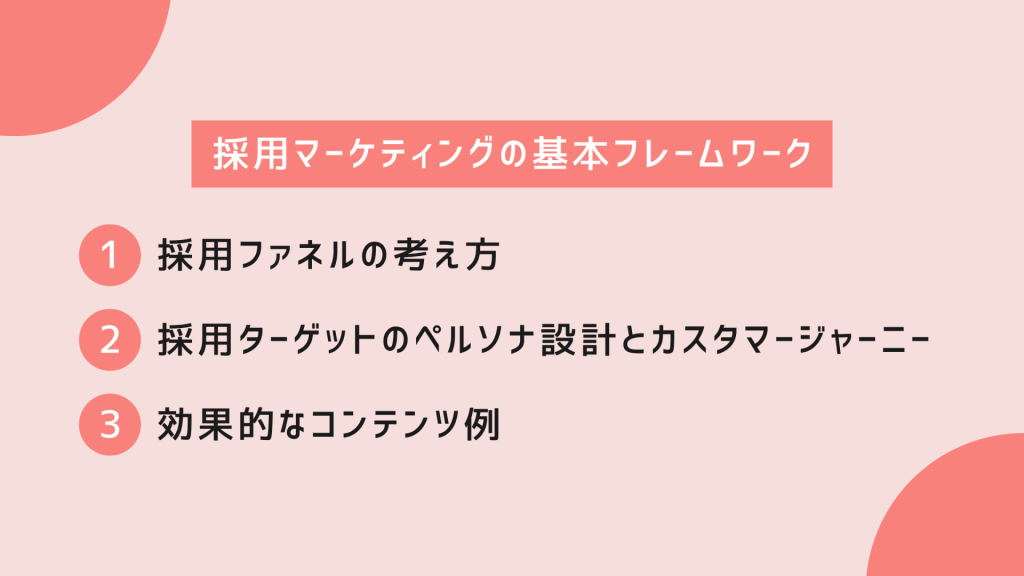
採用マーケティングを効果的に進めるには、感覚や経験に頼るのではなく、全体を見通した“設計図”が必要です。
求職者が企業を認知し、興味を持ち、比較・検討し、応募に至るまでのプロセスをいかに設計するか。それが、採用成功の可否を大きく左右します。
このプロセスには、マーケティングの世界で活用されている「ファネル」や「ペルソナ」「カスタマージャーニー」などのフレームワークがそのまま応用できます。採用活動を一つの“顧客獲得プロセス”と捉えることで、属人的な採用から脱却し、再現性のある運用へと進化させることができるのです。
この章では、採用マーケティングを構造的に実践していくために必要な基本フレームワークについて、順を追って解説していきます。
採用ファネルの考え方
採用マーケティングの基本として押さえておきたいのが、「採用ファネル」の概念です。これは、候補者が企業を認知してから入社に至るまでのプロセスを段階ごとに可視化する考え方で、マーケティングにおける「購買ファネル」を採用活動に応用したものです。
一般的な採用ファネルは次のように構成されます。
認知:会社や募集職種を知る
興味:企業や仕事内容に興味を持つ
応募:選考にエントリーする
選考:面接や試験などのプロセスに進む
内定・入社:企業を選び入社を決定する
このように段階を分けて捉えることで、「どのフェーズで候補者が離脱しているのか」「改善すべき接点はどこか」といったボトルネックを把握しやすくなります。
たとえば、認知から興味への移行率が低ければ、採用広報やコンテンツに課題があるかもしれませんし、応募から選考の歩留まりが悪ければ、求人情報の訴求内容や選考体験を見直す必要があります。
採用ファネルは、単に応募数を追うのではなく、“応募までの前段階”にある重要な接点を見逃さずに設計するための指標です。これにより、属人化した採用活動を、再現性のある「仕組み」へと進化させることが可能になります。
採用ターゲットのペルソナ設計とカスタマージャーニー
採用マーケティングを実践するうえで欠かせないのが、「誰に届けるか」を明確にするペルソナ設計です。
ペルソナとは、理想とする採用ターゲット像を具体化した人物モデルのこと。年齢や職種、経験年数だけでなく、志向性・価値観・転職理由・情報収集手段までを言語化することで、採用施策の精度が格段に高まります。
たとえば、「20代後半・SaaS営業経験3年・成長環境を求める・SNSから情報収集する」といったペルソナを描ければ、WantedlyやTwitterなどを活用した訴求が有効だと判断できます。逆に「40代・マネジメント経験あり・安定志向・家族との時間を重視」といったペルソナであれば、メッセージのトーンや採用チャネルも大きく変わるはずです。
そしてペルソナとセットで重要になるのが、「カスタマージャーニー(候補者の意思決定の流れ)」の設計です。候補者が企業を知ってから応募・入社に至るまでのタッチポイントを時系列で可視化することで、各フェーズで“どんな情報”を“どの手段”で届けるべきかが明確になります。
たとえば、
・認知フェーズではSNSやオウンドメディアで企業文化を伝える
・興味フェーズでは社員ストーリーやキャリアパスを紹介
・応募検討フェーズでは働くメリットや選考情報を具体的に発信
といったように、ジャーニーごとに接点を設計していくことで、「知ってもらう→共感してもらう→動いてもらう」流れを戦略的にコントロールできるようになります。
感覚ではなく設計で採用を動かす。それがペルソナとカスタマージャーニーを活用する最大の意義です。
効果的なコンテンツ例(募集記事、ストーリー、動画など)
採用マーケティングにおいて、「どのような情報を、どんな形式で発信するか」は非常に重要です。候補者が企業を知り、理解し、応募を決断するまでには、複数の接点(タッチポイント)があります。そこで有効なのが、各フェーズに応じたコンテンツ設計です。
1. 募集記事:採用の“入り口”を整える
従来の求人票ではなく、「読み物」としての構成を意識した募集記事が効果的です。特にWantedlyなどの共感型媒体では、以下の要素がポイントです。
- 会社の“想い”や“目指す未来”を語る
- ターゲットに刺さる「課題感」と「やりがい」を提示
- 入社後に得られる成長機会や役割を明確にする
- キャッチコピーや見出しにも工夫を凝らす
2. 社員ストーリー・インタビュー:人を通じてカルチャーを伝える
実際に働く社員の声を届けることで、候補者は「自分が働く姿」を具体的に想像できます。
たとえば:
- 入社理由と現在の業務内容
- 成長を実感できたエピソード
- チームの雰囲気や働く価値観
これらはテキスト・写真・動画など形式を問わず活用でき、「共感」を生むコンテンツとして有効です。
3. 動画:数分で“空気感”まで届けられるツール
動画は、テキストでは伝えきれない“雰囲気”を届けられる強力な手段です。特に若手人材との接点づくりに有効で、以下のような形式が活用されています。
- 会社紹介・オフィスツアー
- 代表・メンバーインタビュー
- 1日の仕事の様子や社員同士の交流風景
SNS(YouTube/Instagram/TikTokなど)と組み合わせることで、認知拡大にもつながります。
採用マーケティングの実践ステップ
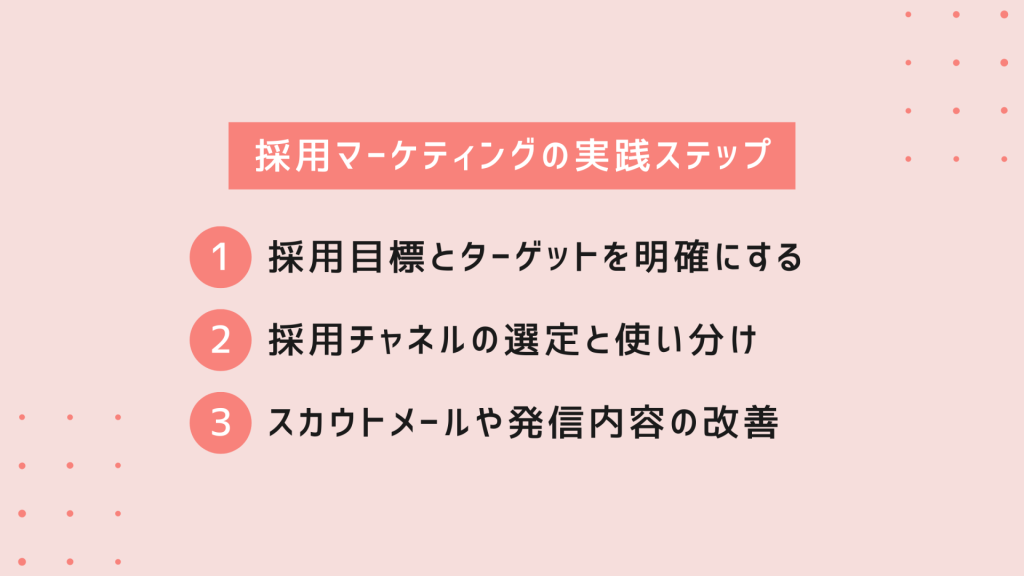
採用マーケティングの概念やフレームワークを理解したら、次に重要なのは「どうやって実践に移すか」です。
理論を知っていても、それが現場の行動や成果に結びつかなければ意味がありません。
採用マーケティングの実践には、採用目標やターゲットの明確化、媒体やチャネルの最適化、そして日々のスカウトやコンテンツ配信の質の向上まで、一貫性と継続性のある運用設計が欠かせません。
この章では、実際に企業が採用マーケティングを取り入れる際に押さえるべき基本ステップを解説します。現場で“すぐに使える”視点を意識しながら、戦略を行動に落とし込むプロセスを見ていきましょう。
①採用目標とターゲットを明確にする
採用マーケティングを実践する上で最初に着手すべきは、「どんな人を、いつまでに、何名採用するのか」という採用目標の明確化です。
この目標があいまいなままでは、施策がブレやすく、マーケティングの効果測定もできません。
たとえば「エンジニアを採用したい」というだけでは不十分です。必要なのは、「開発体制を強化するために、半年以内にフロントエンド経験3年以上のTypeScriptエンジニアを2名採用する」といった、事業計画とリンクした具体的な目標設定です。
また、目標を定めたら、それに応じて「採用ターゲット」を言語化することも重要です。
ターゲット設計では、年齢・職種経験・志向性などを軸にペルソナ(理想人材像)を作成します。
年齢層 :25〜30歳の第二新卒〜若手中堅層
職種経験:Web業界での法人営業経験2〜3年程度
スキル :無形商材の提案力、CRMを活用した顧客管理経験
志向性 :裁量のある環境で成長したい、組織づくりに興味がある
転職理由:現職での評価制度やキャリアパスに不安を感じている
行動特性:WantedlyやTwitterで情報収集、スタートアップイベントにも参加
このように、人数(量)だけでなく、どんな人物像(質)を求めているのかを明らかにすることが、すべての採用施策の起点となります。
採用は“欲しい人を集める活動”であると同時に、“自社に合う人と出会う設計”です。
目指すゴールとターゲットが定まれば、媒体選定、コンテンツ設計、スカウト運用すべてがブレずに連動していくのです。
②採用チャネルの選定と使い分け
採用目標とターゲット像が明確になったら、次に重要なのが「どのチャネルを使ってアプローチするか」の選定です。
どれだけ理想的なターゲット像を描いても、その人たちが集まっていない場所に情報発信していては、出会うことすらできません。
採用チャネルとは、求職者との接点となる“場”のことを指します。代表的なものとしては、求人媒体(広告)、ダイレクトリクルーティング(スカウト)、リファラル採用、採用イベント、自社サイト、SNSなどが挙げられます。
たとえば、20代の若手・カルチャーフィット重視層をターゲットとする場合は「Wantedly」や「X(旧Twitter)」、エンジニア・クリエイター系の即戦力人材には「Green」「レバテックダイレクト」などが候補になります。
一方で、業務委託・副業人材なら「YOUTRUST」や「複業クラウド」なども視野に入るでしょう。
重要なのは、「誰に届けたいのか」と「その人はどこにいるのか」をセットで考えること。媒体やチャネルはターゲットによって最適解が異なります。
また、チャネルごとの特徴を理解し、役割を使い分けることも成果を左右します。
求人広告 :母集団形成を目的とした“広く届ける”手段
ダイレクトリクルーティング:ターゲット人材へ“狙って届ける”手段
リファラル採用 :社内のつながりを活用し“信頼ベースで届ける”手段
SNS・オウンドメディア :企業理解・共感を“深める”手段
特に中小企業やベンチャーでは、“人”そのものが最大の魅力になります。形式的な条件だけでなく、感情に訴えるリアルな発信こそが、応募の後押しになるのです。
【関連記事】採用媒体はどう選ぶ?目的別の媒体比較と失敗しない選定ポイント
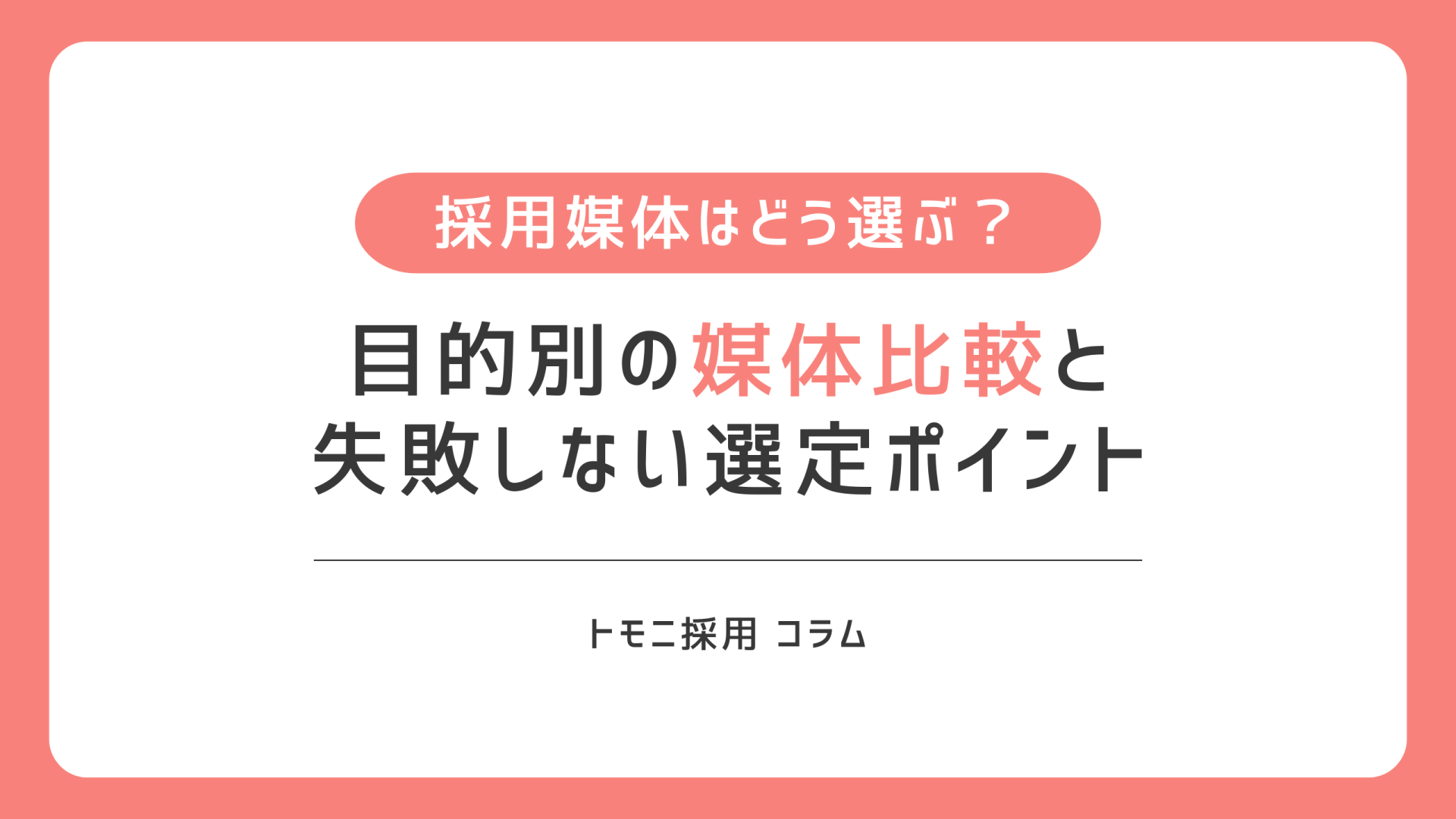
③スカウトメールや発信内容の改善
採用マーケティングにおいて、スカウトメールは“最前線のコミュニケーション”です。
特にダイレクトリクルーティングを活用している企業にとって、スカウトの質は応募率や面談化率に直結します。にもかかわらず、「テンプレートを送って終わり」「担当者によって文面に差がある」といった状態では、採用成果につながりません。
重要なのは、ターゲットの興味・価値観に合わせた“パーソナライズ”された文面設計です。
例えば以下のような構成が基本となります:
・冒頭で「なぜあなたに送っているのか」を明確にする(経歴への言及)
・企業のミッションや事業の魅力を“応募者目線”で語る
・募集ポジションの役割やキャリアに与える影響を伝える
・カジュアルに話せる場(カジュアル面談)の提案
また、スカウトメールの改善には配信タイミングや通数の最適化、返信後の対応スピードも重要な要素です。
どれだけ良い文面でも、候補者がオンラインでない時間帯に届いていたり、返信に数日かかっていては機会損失につながります。加えて、個別対応力を強化するためには運用体制の整備も欠かせません。
スカウト業務を特定の担当者に任せきりにせず、KPIの共有や定期的な振り返りをチームで行うことで、ナレッジの蓄積と再現性の高い運用が実現できます。
このように、スカウトは「配信する作業」ではなく、「候補者との最初の関係構築」であるという認識を持つことが大切です。文面の工夫・設計・運用体制まで含めて改善していくことで、スカウトは“押しつけ”ではなく“共感の入り口”となり、質の高い母集団形成が可能になります。
【関連記事】スカウトメール、誰が送る?成功率を上げる運用体制
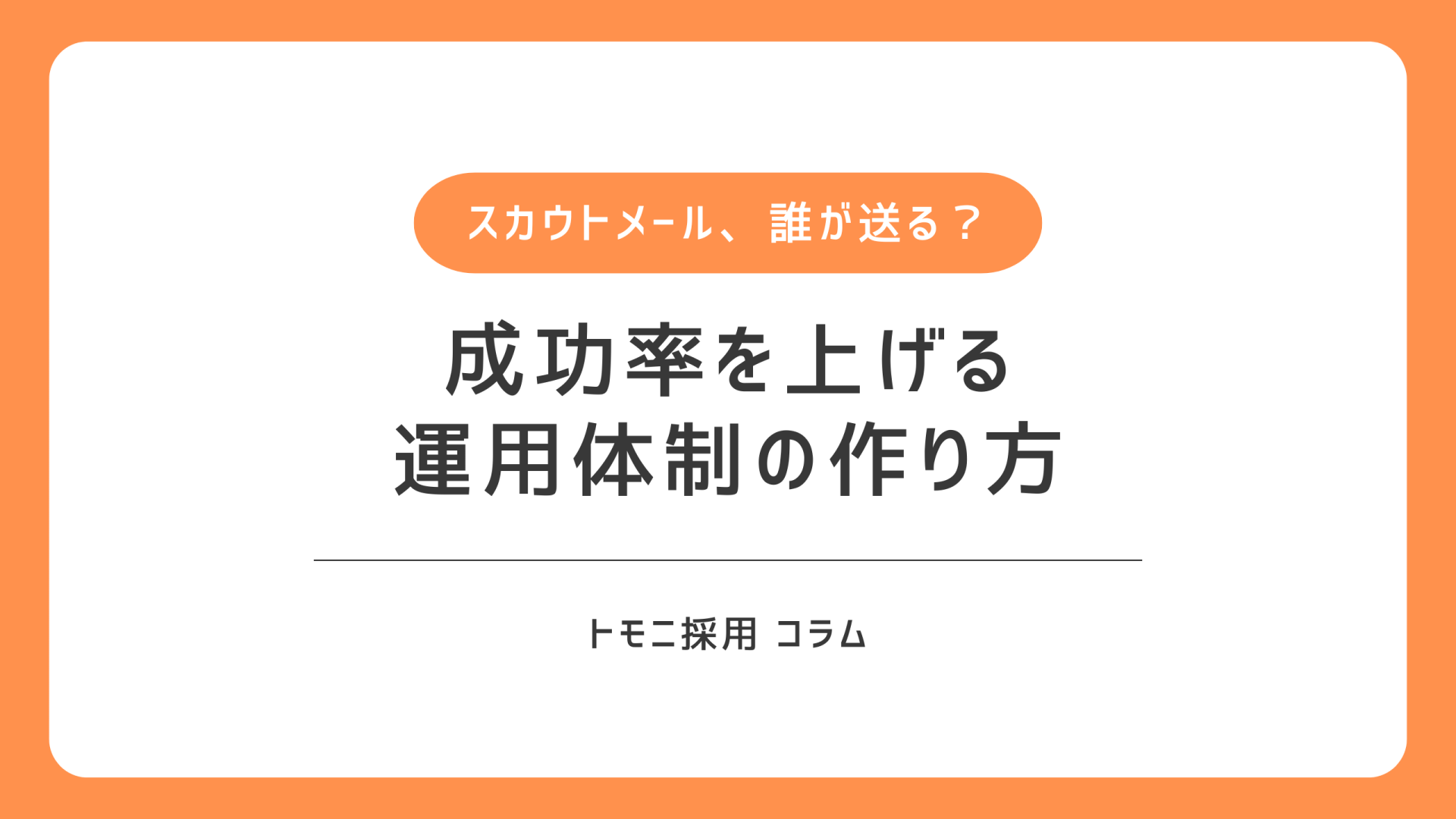
採用ブランディングとの違いと共通点
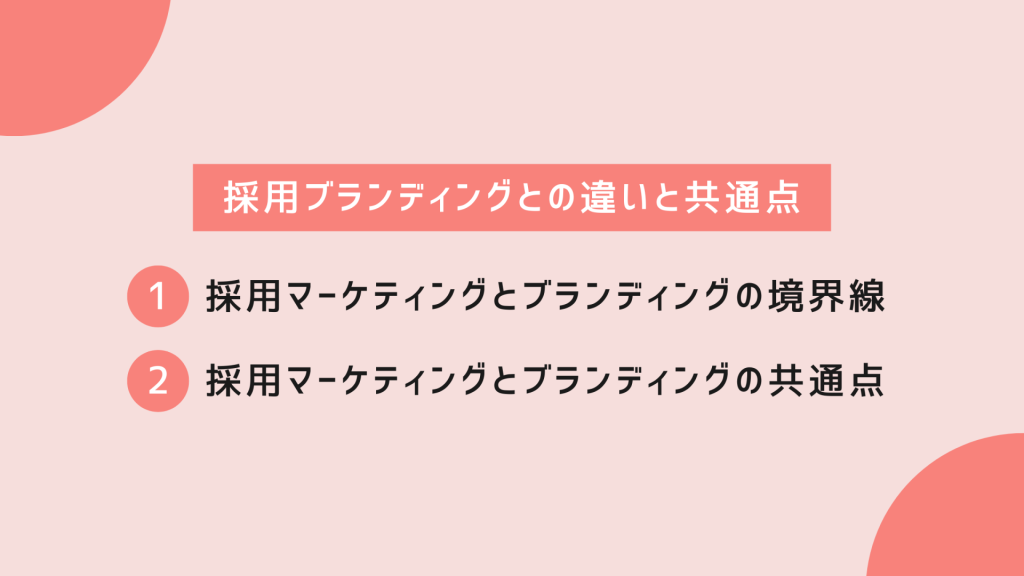
採用マーケティングとあわせて語られることが多いのが「採用ブランディング」です。
どちらも“候補者から選ばれる企業になるための取り組み”という点では共通していますが、その役割やアプローチには明確な違いがあります。
採用マーケティングは、届け方や接点の作り方に焦点をあてた“施策設計”であるのに対し、採用ブランディングは、企業として「何を伝えるべきか」「どんな魅力があるのか」を定義する“土台づくり”の側面が強いと言えます。
この章では、両者の関係性とそれぞれの役割を整理し、採用活動全体の中でどう組み合わせて活用すべきかを解説していきます。
採用マーケティングとブランディングの境界線
採用マーケティングと採用ブランディングは、どちらも「候補者から選ばれる企業」を目指すうえで重要な取り組みですが、役割とアプローチには明確な違いがあります。この境界線を理解することで、採用活動全体に一貫性を持たせ、成果につなげることができます。
まず、採用ブランディングは、企業が“どんな組織でありたいか”を定義し、それを社内外に発信していく活動です。具体的には以下のような内容が含まれます:
採用ブランディン
・自社の価値観・文化・ビジョンの言語化
・理想の社員像やチーム像の明確化
・「働く意味」や「やりがい」のストーリー化
・社員インタビューやカルチャーデックの作成
一方で、採用マーケティングは、それらブランディングで定めたメッセージや魅力を、適切なターゲットに向けて届ける“実行戦略”です。主なアプローチは以下の通りです:
採用マーケティング
・ペルソナ設計とチャネル選定(媒体・SNSなど)
・ファネル設計とコンテンツ配信計画
・スカウト文面の最適化や応募率の検証・改善
・広告出稿やLPのA/Bテスト
要するに、採用ブランディング=「何を伝えるか(コンセプト・中身)」、採用マーケティング=「どう伝えるか(手段・届け方)」に整理できます。
たとえば、「社員の自律性を大切にする会社」というブランドを掲げている場合、それを伝える方法としては、スカウト文面で裁量ある働き方を紹介したり、Wantedlyで実際の業務風景を記事化したりするのがマーケティングの役割です。
両者は別々ではなく、ブランディングを“軸”として、マーケティングで“波及”させていく関係です。どちらか一方に偏ることなく、連動させて運用することが、選ばれる企業づくりには不可欠です。
採用マーケティングとブランディングの共通点
採用マーケティングと採用ブランディングは、それぞれ役割こそ異なりますが、目指す方向性には多くの共通点があります。
両者をうまく連携させることで、単発的な応募獲得ではなく、中長期的な採用力の向上につながります。
共通点の一つは、どちらも「候補者に選ばれるための視点」に立っているということです。求人情報やスカウト文面はもちろん、企業のSNS投稿、社員の声、採用イベント、あらゆる接点で企業の印象が形作られています。
マーケティングもブランディングも、単なる情報発信ではなく、「どう見られ、どう感じてもらい、どう行動してもらうか」を考えるという意味で、本質的には同じ思想のもとにあります。
また、両者に共通するキーワードは以下の通りです:
ターゲット志向:
自社が伝えたいことではなく、候補者が知りたいこと・価値を感じることを軸に設計
一貫性のあるメッセージ:
媒体ごとに内容がブレると信頼を失うため、すべての発信に統一感が必要
体験の最適化(CX):
応募前の接触〜選考〜入社までを一連の“候補者体験”として捉える
企業らしさの言語化と可視化:
抽象的な魅力を、具体的なエピソードやビジュアルで伝える
たとえば、採用ブランディングで打ち出した「風通しの良い組織風土」を、スカウト文面で上司との1on1文化に触れることで伝えたり、Wantedlyでチームインタビューを発信することで裏付けをつけたりすれば、ブランディングがマーケティングに活きる形で機能します。
つまり、採用マーケティングとブランディングはそれぞれの立場で「企業の魅力をどう伝え、どう選ばれるか」を設計している点で本質的に共通しています。
部分最適ではなく、全体最適の視点で連携・運用することが、採用成果の質と量の両立につながるのです。
よくある失敗と成功する企業の共通点
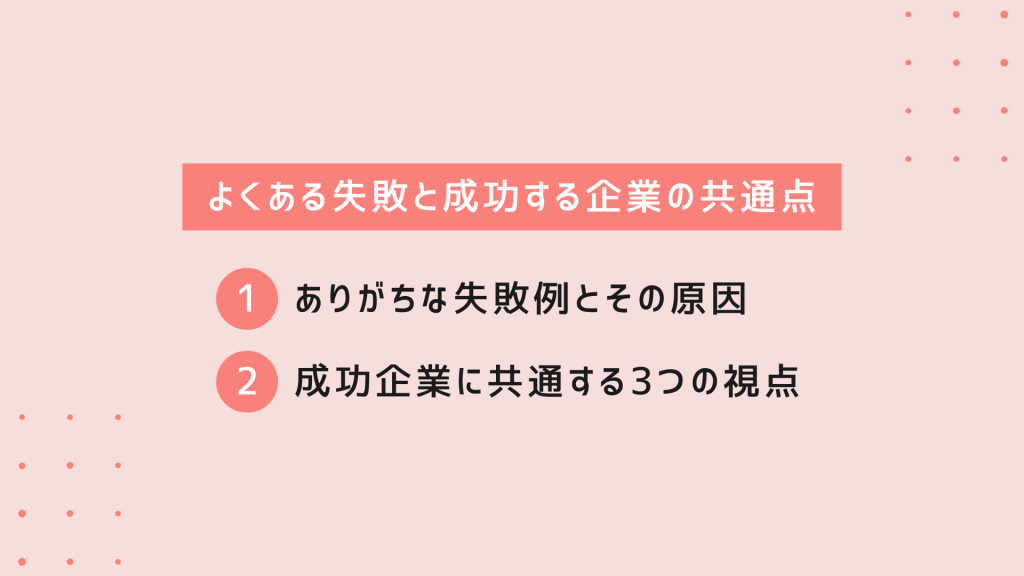
採用マーケティングの重要性が広く認識されるようになった一方で、実際には「施策を始めたけれど成果が出ない」「形だけ導入して終わっている」といった企業も少なくありません。
成功する企業とそうでない企業の違いは、リソースや知名度ではなく、考え方と運用の精度にあります。どんなに優れたツールや施策を導入しても、目的が曖昧なまま進めてしまえば、結果にはつながりません。
この章では、採用マーケティングにおいて陥りがちな失敗パターンを整理した上で、継続的に成果を上げている企業に共通する視点や行動を解説します。
ありがちな失敗例とその原因
採用マーケティングに取り組む企業は増えていますが、そのすべてが成果を出しているわけではありません。よくある失敗には共通した“落とし穴”があり、ほとんどが「戦略の欠如」や「運用の形骸化」に起因しています。
以下に、実際によく見られる失敗パターンとその原因を整理します。
失敗例①:ペルソナが曖昧なまま施策を進めてしまう
ターゲットが明確でないまま、とりあえずスカウトを配信したり、求人広告を出したりしても、母集団形成の質が上がらず、応募者とのミスマッチが起きやすくなります。
原因:社内で採用要件が擦り合っておらず、「誰に来てほしいか」が言語化できていない。
失敗例②:チャネルの選定を誤っている
自社に合わない媒体やスカウトサービスに依存してしまい、想定ターゲットに届いていないケースです。「若手を採用したいのに、ミドル層向けの媒体に出稿している」といったズレが典型です。
原因:チャネルの特徴を理解せず、なんとなくの判断で媒体を選んでいる。
失敗例③:発信コンテンツが“自分目線”になっている
求人票やスカウトメール、SNS投稿が「会社の都合」だけで書かれており、候補者の共感や関心を得られていないパターンです。
原因:求職者の情報収集行動や価値観を理解せず、届け方を工夫していない。
失敗例④:施策の振り返りをせず、改善が止まる
一度配信したら終わり、広告を出したら放置、という状態では、成果は一時的なものに留まります。
原因:KPI設計や振り返りのプロセスがなく、PDCAが回っていない
このように、失敗の多くは戦略設計の不足と運用精度の低さに集約されます。
「いいことをやっているはずなのに結果が出ない」と感じたときは、まずはこれらのパターンに当てはまっていないかをチェックしてみることが重要です。
成功企業に共通する3つの視点
採用マーケティングに取り組んで、着実に成果を出している企業には、共通する“考え方の土台”があります。派手な施策や高額なツールを使っているわけではなく、むしろ地に足のついた取り組みを丁寧に積み重ねています。
ここでは、成果を出している企業に共通する3つの視点をご紹介します。
視点①:「採用=経営活動」として位置づけている
成功企業は、採用を単なる“人事部の仕事”としてではなく、経営戦略と直結する活動として捉えています。事業成長に必要な人材像を言語化し、現場・経営層と連携して採用要件を固めているため、施策に一貫性があります。
この姿勢があることで、コンテンツや打ち出すメッセージにもブレがなくなり、求職者からの共感を生みやすくなります。
視点②:「仕組み化」にこだわっている
感覚的・属人的な採用から脱却し、KPI管理・ファネル分析・改善PDCAなど、再現性ある仕組みを構築しているのも成功企業の特徴です。
たとえば、スカウト返信率や面談化率を定期的に可視化し、「どの文面・タイミング・担当者が成果を出しているか」を分析。うまくいった事例を横展開して、チーム全体の底上げにつなげています。
視点③:「採用はマーケティング&ブランディング」と認識している
成功企業は、採用活動を情報発信やコミュニケーションの場と捉え、“自社らしさ”を一貫して届ける重要なタッチポイントと認識しています。
WantedlyやSNSで日常の社風を発信したり、スカウト文面や面談でもカルチャーを丁寧に伝えるなど、マーケティングとブランディングの両面を意識した採用運用が徹底されています。
これら3つの視点を持つことで、施策が表面的なものにならず、候補者との“本質的な関係構築”に繋がっていきます。
採用マーケティングを単なる手法で終わらせず、戦略と思想のレベルに引き上げることが、成果を出す企業の共通点なのです。
まとめ|マーケティング視点で採用活動を再設計しよう
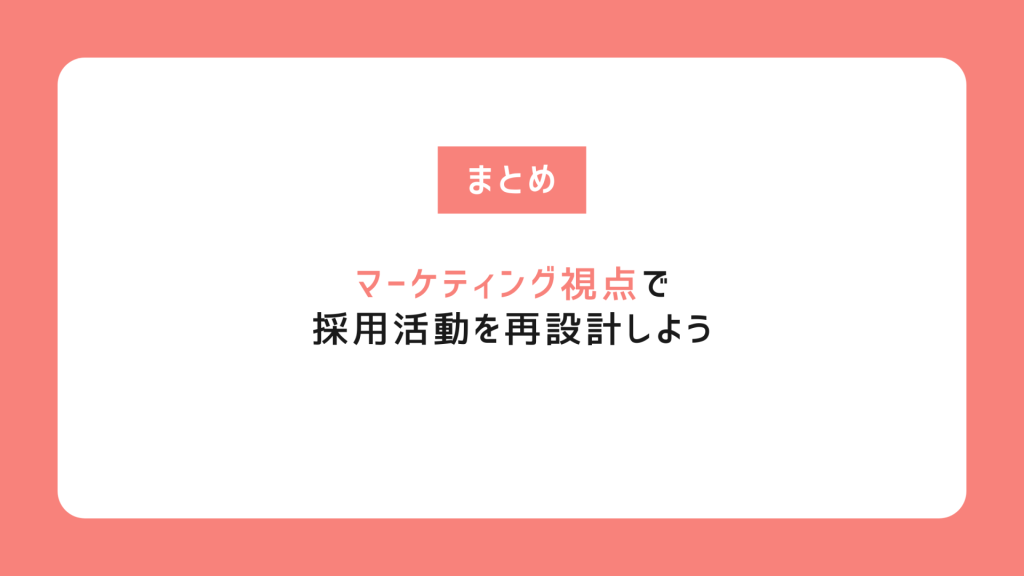
採用市場の変化が加速するなかで、企業が人材を“選ぶ”時代から、“選ばれる”時代へと移行しています。その中で求められているのが、マーケティングの視点を取り入れた採用活動の再設計です。
この記事では、採用マーケティングの定義や必要性から始まり、実践のステップ、ブランディングとの関係性、そして成功・失敗の事例までを解説してきました。
共通して言えるのは、成果を出している企業ほど、「誰に、何を、どう届けるか」を明確にし、採用を戦略的かつ継続的なプロセスとして設計しているということです。
もし今、採用活動において以下のような課題を感じているのであれば、それはマーケティングの力で改善できるかもしれません。
- 応募数が集まらない、もしくはターゲットとズレた応募が多い
- スカウトの返信率や応募率が伸びない
- 会社の魅力をうまく伝えきれていない気がする
- 採用活動が属人化しており、再現性がない
こうした課題に対して、マーケティングの考え方は“施策”ではなく“思考法”として機能します。
今ある施策の見直しだけでなく、企業全体として「誰から、なぜ選ばれる企業になるか」を再定義するきっかけになるはずです。
採用マーケティングは、一部の大手企業だけのものではありません。人材獲得に真剣に向き合うすべての企業にとって、取り入れるべき“採用の新しい常識”です。
ぜひ、今日からできる小さな一歩から取り組んでみてください。
【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】
株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。
私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。
「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!
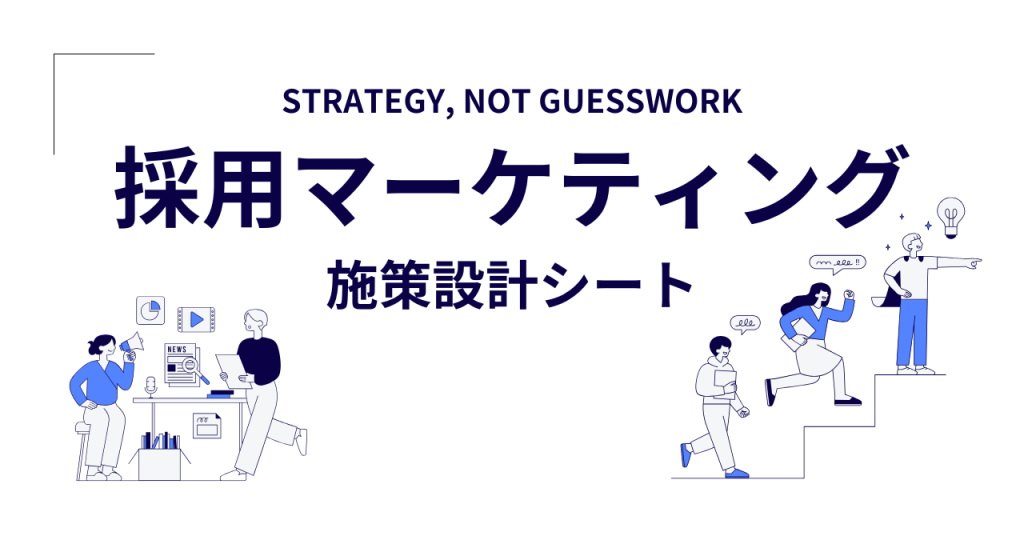
採用マーケティング施策設計シート
採用マーケティングを“なんとなく”で終わらせないために。
ターゲット設計や媒体選定、KPI設定など、考えるべき項目を1枚にまとめた実践用ワークシートです。明日からの採用施策にすぐ使えます。