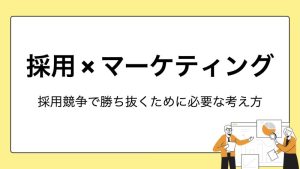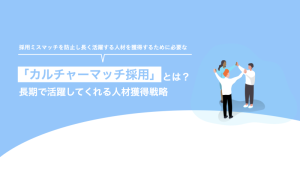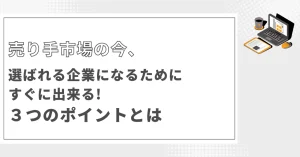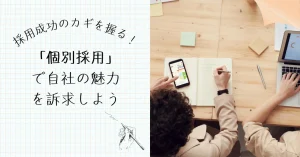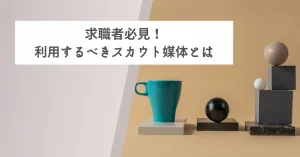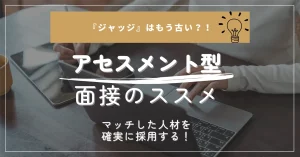採用の外注活用ガイド|外注で効率化できる業務と自社で担うべき業務の境界線
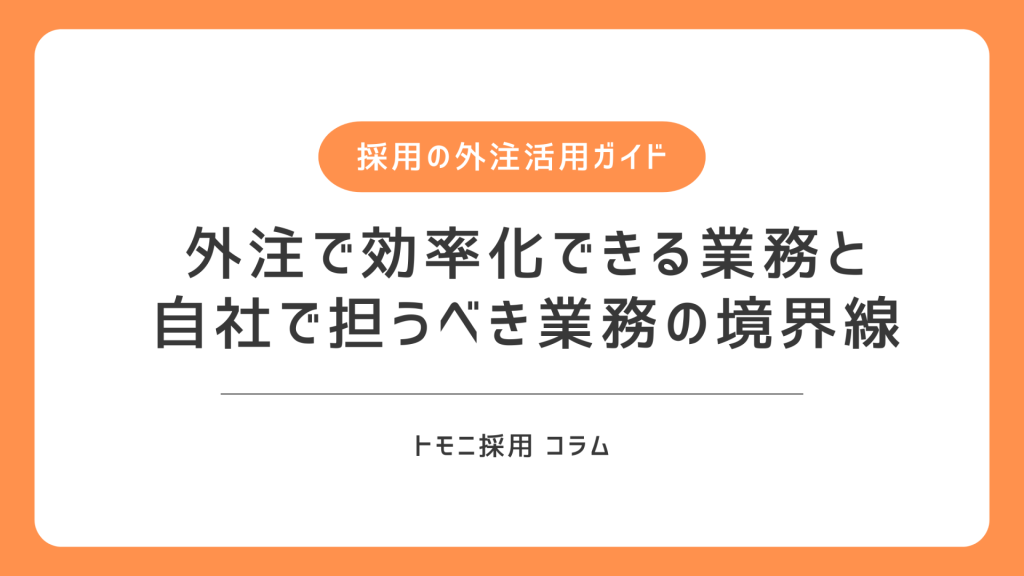
採用活動の現場では、「本当に自社でやるべき業務」と「外部に任せた方が効率的な業務」の線引きが曖昧になりがちです。
求人媒体の運用、スカウトメールの配信、応募者対応、どれも採用成果に直結する重要なプロセスですが、限られた人事リソースで全てを内製化しようとすると、担当者の負担が増し、戦略的な採用活動に手が回らなくなってしまいます。
そこで注目されているのが、RPOや媒体運用代行といった「外注」の活用です。
本記事では、採用業務をどのように切り分け、外注すべき領域と自社で担うべき領域を整理することで、成果と効率を両立させる方法を解説します。
なぜ採用業務を外注する企業が増えているのか
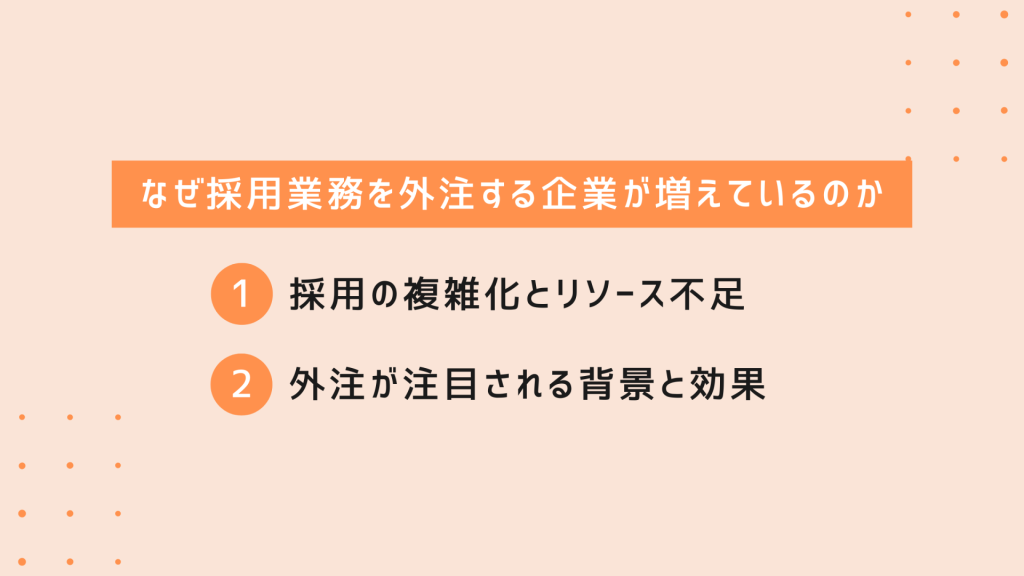
人材獲得競争が激化する中、多くの企業が「採用業務の一部を外注する」選択肢を取るようになっています。
これまで採用は自社の人事部門が担うべき領域とされてきましたが、求人媒体の多様化、候補者へのアプローチ方法の複雑化、応募者対応の煩雑さなどにより、従来のやり方では限界を感じる企業が増えているのが実情です。
特に中小企業や急成長中のスタートアップでは、限られた人員で採用計画から運用までを同時並行で進めることが難しく、「戦略的な採用活動にリソースを集中するために、業務の一部をプロに任せたい」というニーズが高まっています。
では、具体的にどのような理由から外注が選ばれているのか、次に詳しく見ていきましょう。
採用の複雑化とリソース不足
採用活動は近年ますます複雑化しています。以前のように求人広告を出せば応募が集まる時代は終わり、現在は求人媒体、ダイレクトリクルーティング、SNS、リファラルなど多様なチャネルを組み合わせて運用する必要があります。
各媒体ごとに特性や運用ノウハウが異なるため、担当者には幅広い知識と継続的な運用が求められます。
一方で、人事部門のリソースは限られており、ある調査では中途採用業務の約6割が求人媒体管理や応募者対応などの定型作業に費やされているといわれます。こうした業務に時間を取られると、候補者との関係構築や採用戦略の策定といった本来重視すべき「コア業務」に十分な時間を割けなくなります。
結果として、短期的な採用数の確保に追われ、長期的な組織づくりが進みにくくなるケースも少なくありません。このため、定型業務を外部に任せ、社内は戦略的な採用活動へ集中する「外注活用」のニーズが急速に高まっているのです。
外注が注目される背景と効果
企業が採用業務の外注を検討する背景には、大きく二つの要因があります。
ひとつは、求人媒体や候補者接点の多様化による業務の煩雑さです。媒体ごとに更新や分析の方法が異なり、さらにスカウト配信や応募者対応を並行して行うとなると、人事担当者の負担は増大します。
もうひとつは、人材獲得競争の激化です。限られたリソースでスピード感を持って動かなければ、優秀な人材を逃してしまうリスクが高まっています。
外注を活用することで、こうした課題に対応できます。定型的な媒体運用や候補者管理を専門チームに任せることで、人事は「面接設計」「カルチャー発信」「採用判断」などコア業務に集中できます。
また、外部のノウハウを取り入れることで、母集団形成の効率や応募者対応のスピードが向上し、結果として採用全体の成果が高まりやすくなります。外注は単なる工数削減ではなく、採用活動を戦略的に進化させる手段として注目されているのです。
外注すべき業務と自社で担うべき業務の切り分け
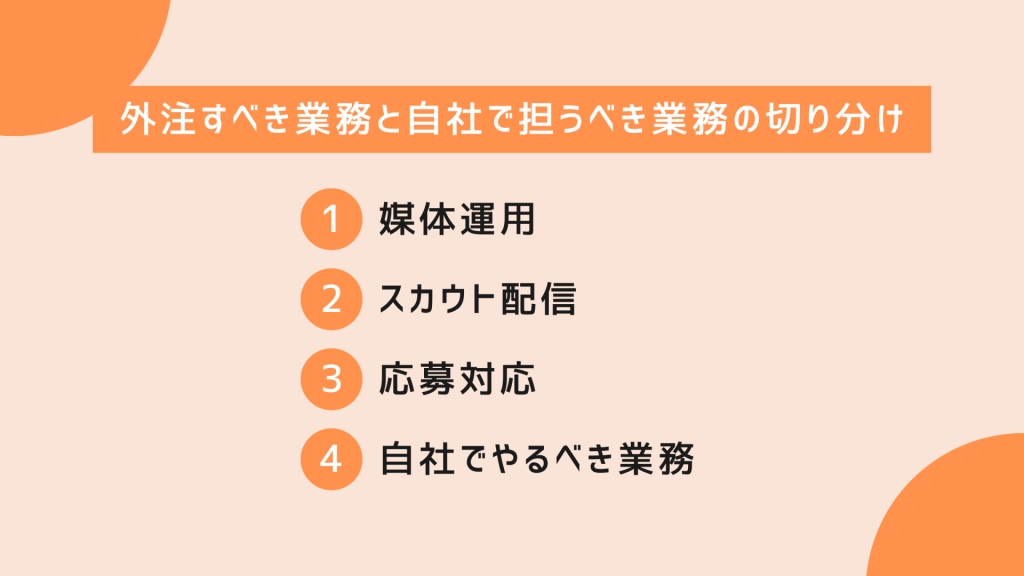
採用業務を効率化するために外注を活用する企業は増えていますが、重要なのは「どの業務を外に任せ、どの業務を自社で担うのか」を正しく見極めることです。
求人媒体の管理やスカウト配信のように専門性や工数が求められる領域は外注の効果が高い一方で、候補者の志向性を理解して魅力を伝える面接や、自社カルチャーを体現するコミュニケーションは社内でしか対応できません。
外注と内製の線引きを誤ると、効率化どころか成果が下がってしまうリスクもあります。ここでは、採用業務を「外注すべき領域」と「自社で担うべき領域」に整理し、実務の切り分け方を解説します。
媒体運用(求人広告・媒体管理)
求人媒体の運用は、多くの企業で外注を検討すべき代表的な業務です。
媒体ごとにアルゴリズムや掲載ルールが異なり、タイトル設計、検索キーワードの最適化、掲載順位の調整、レポート分析など、専門的な知識と継続的な運用が欠かせません。さらに、複数の媒体を同時に利用する場合、それぞれの管理画面を行き来して効果を比較し、改善サイクルを回す必要があり、人事担当者にとって大きな負担となります。
求人媒体の運用は、外注の効果が最も大きく出やすい領域のひとつです。媒体ごとに仕組みやアルゴリズムが異なるため、専門知識と継続的な分析が不可欠になります。
媒体運用で発生する主な業務:
求人票の作成・更新
∟タイトルや本文の訴求力を高める
∟検索にヒットしやすいキーワードを最適化
∟定期的な更新による媒体内での露出維持
掲載順位や表示ロジックの調整
∟各媒体のアルゴリズムを理解し、クリック率を改善
∟表示順位や見え方を工夫して、候補者の目に留まりやすくする
効果測定・レポート分析
∟PV数、応募数、有効応募率を定期的にチェック
∟応募数は多いが有効応募が少ない、などの課題を発見
改善施策の実行
∟ABテストでタイトルや本文の効果を比較
∟競合他社の出稿状況を踏まえて差別化ポイントを強化
複数媒体の並行管理
∟媒体ごとの特性を把握し、応募傾向を分析
∟効果の高い媒体に予算や工数を集中させる
これらをすべて自社で対応すると、人事担当者の工数は膨大になり、戦略的な業務に時間を割けなくなります。
外注を活用するメリット
・専門チームによる応募数・有効応募率の最大化
・データに基づく改善サイクルの高速化
・競合他社の出稿状況を踏まえた柔軟な媒体戦略
一方で、以下は自社で担うべき業務です。
・採用要件の設定(どのような人材を採用したいのか)
・成果の判断基準の決定(量か質か、どこに重点を置くか)
外注を活用すれば、これらの煩雑な作業を専門チームが担い、応募数や有効応募率の最大化に直結する施策を効率的に実行できます。
例えば、求人票のタイトルや訴求ポイントをABテストで改善したり、競合企業の動向を踏まえて掲載枠を調整したりと、自社だけでは難しい運用が可能になります。
その一方で、「どういう人材を採用したいのか」という採用要件の設定や、成果の判断基準は自社が主体的に決めるべき領域です。外注と内製の役割を明確に分けることで、媒体運用の効果を最大限に引き出すことができます。
スカウト配信(候補者リスト化と文面最適化)
スカウトは、「欲しい人材に直接アプローチできる」最も効果的な採用手段のひとつです。しかし、実際に運用してみると、候補者リストの抽出から文面作成・送信管理まで多くの工数がかかり、自社だけで効率的に回すのは容易ではありません。
スカウト配信に必要な主な業務:
候補者リストの選定
∟各種条件(職種・スキル・勤務地など)で候補者を検索
∟応募可能性の高い人材を見極めてリスト化
スカウト文面の作成・最適化
∟応募者の心を動かすタイトル・本文の設計
∟ターゲットごとにカスタマイズしたメッセージ配信
送信・効果測定
∟改善点を分析し、次回のスカウトに反映
∟送信タイミングの調整
∟開封率・返信率・応募率のモニタリング
外注を活用するメリット
・豊富なノウハウを持つ代行会社による 高精度の候補者選定
・返信率が高い文章の作成や、応募につながりやすい表現の工夫
・運用代行による工数削減と、社内リソースの有効活用
・外部の市場データやトレンドを活かしたアプローチの実現
一方で、「どのような人材を求めるのか」や「自社の魅力をどう伝えるか」といった核となる部分は、自社で明確にする必要があります。
外注はその方針を具体的なアクションに落とし込み、成果を最大化する役割を担うのです。
【関連記事】スカウト配信代行と自社運用の違いとは?成果・スピード・体制の差を検証
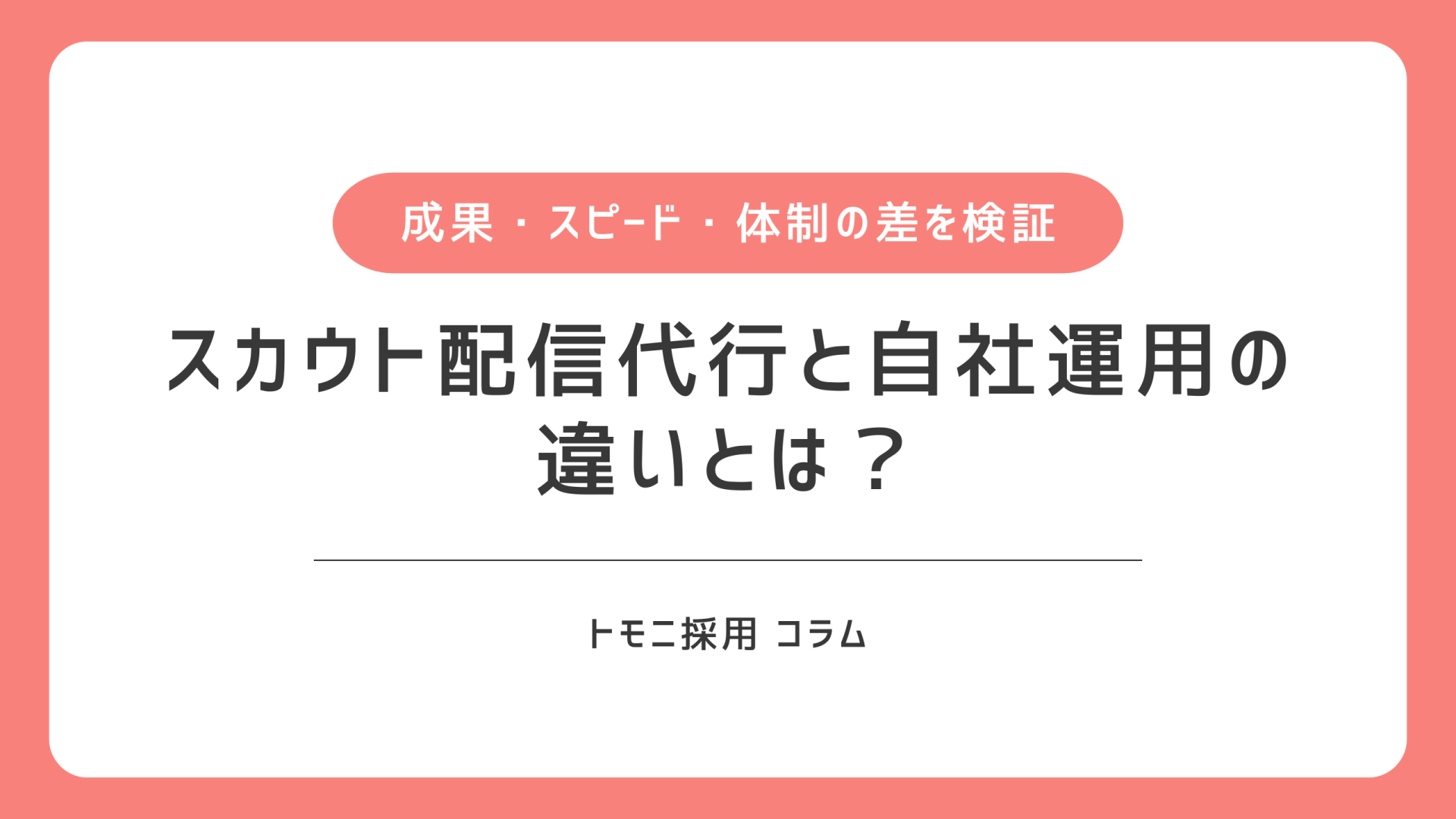
応募対応(候補者連絡・スクリーニング)
応募者が発生した後の初期対応は、採用体験(CX)に大きく影響します。返信が遅れたり連絡が不十分だったりすると、候補者の志望度は一気に下がり、辞退や離脱につながりかねません。
そのため、応募対応はスピードと正確さが求められる業務ですが、日常的な負担も大きいため外注の活用価値が高い領域です。
応募対応で発生する主な業務:
応募者への一次連絡
∟応募受付メールの送信
∟応募書類の回収・管理
スクリーニング(一次判断)
∟職務経歴やスキルの要件確認
∟不足情報のヒアリング
面接調整・リマインド
∟面接日程の調整(候補者と現場担当のスケジュール調整)
∟リマインドメールの送付、当日の案内
応募者データ管理
∟選考ステータスの更新
∟ATSやスプレッドシートへの登録
外注を活用するメリット
・対応スピードの向上:即日対応が可能になり、候補者の志望度低下を防止
・業務負担の軽減:煩雑なメール・スケジュール調整を代行
・精度の高いスクリーニング:経験豊富な担当者による一次判断
・選考体験の向上:候補者にとって安心感のあるスムーズな対応
ただし、応募対応をすべて外部に任せるのではなく、最終的な合否判断やカルチャーマッチの見極めは自社で行うことが不可欠です。
外注を上手に活用することで、定型業務の負担を減らしつつ、候補者との接点で重要な部分にリソースを集中できます。
自社でやるべき業務(カルチャー発信・面接・採用判断)
外注を活用することで定型業務の効率化は可能ですが、すべてを外部に任せてしまうと「その会社らしさ」が候補者に伝わりにくくなります。
採用成功のカギは、企業独自の文化や価値観を候補者に直接届けることにあります。そのため、以下のような業務は自社が担うべき領域です。
自社で担うべき主な業務:
カルチャー発信
∟社員インタビューや社内イベントの発信を通じて、働く魅力を候補者に伝える
∟SNSやオウンドメディアで「自社らしさ」を可視化し、共感を生む
∟候補者が「この会社で働きたい」と思える採用ブランディングを強化
面接(一次・二次・最終)
∟候補者の人柄やカルチャーマッチを見極める場
∟自社メンバーが直接コミュニケーションをとることで、候補者に安心感を与える
∟現場社員や経営層の参加により、候補者が働くイメージを具体化できる
採用判断
∟スキルだけでなく「自社で活躍できるか」を見極める最終的な意思決定
∟候補者の志向性と組織の将来像を照らし合わせる
∟内定通知時には、経営者や現場からの直接的なメッセージを伝えることで入社意欲を高める
なぜ自社で担うべきか
・企業文化や価値観は外部では表現しきれない
・面接での「温度感」や「相性の確認」は現場でしか判断できない
・採用判断は組織づくりの核心であり、経営戦略とも直結する
つまり、オペレーションは外注、カルチャーや意思決定は自社という役割分担を徹底することで、効率と独自性を両立させることができます。
外注活用で得られるメリットとリスク
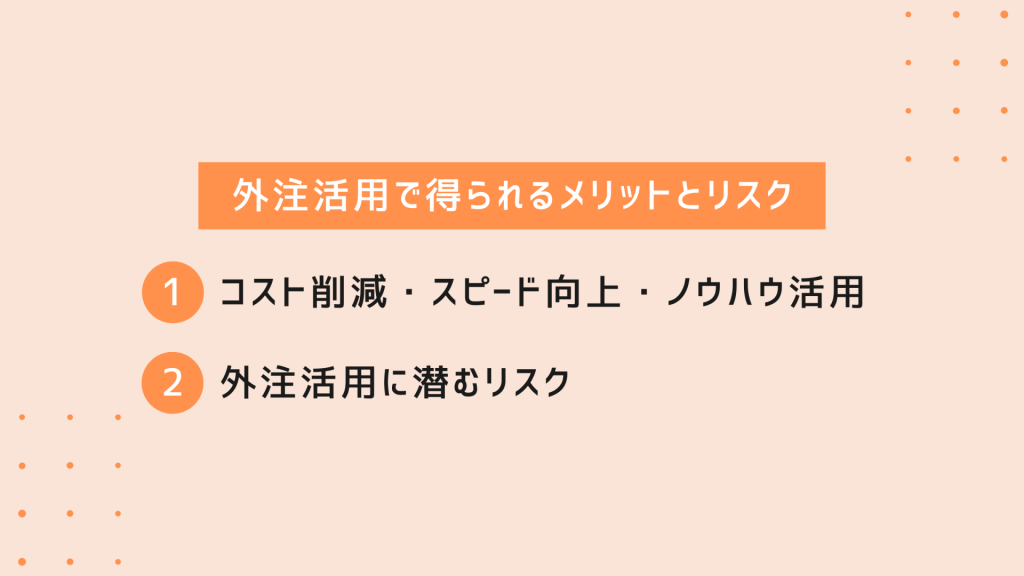
採用業務の一部を外注することで、限られたリソースを戦略的な活動に集中できるのは大きな魅力です。媒体運用やスカウト配信、応募対応といった定型業務を任せることで、効率化やスピードアップ、そして専門ノウハウの活用が可能になります。
しかし同時に、情報共有不足によるミスマッチや、自社の採用方針とのズレといったリスクが生じる点も無視できません。外注は「万能の解決策」ではなく、メリットとリスクを正しく理解し、自社の状況に合わせて活用することが重要です。
ここでは、外注活用によって得られる効果と注意すべきポイントを整理します。
メリット:コスト削減・スピード向上・ノウハウ活用
採用業務を外注する最大の利点は、単なる工数削減にとどまらず、成果を高める仕組みを効率的に取り入れられることです。
ここでは特に効果が大きい「コスト削減」「スピード向上」「ノウハウ活用」の3つのメリットを整理します。
外注で得られる主なメリット
1. コスト削減
・運用業務を外注し、残業や追加人員コストを削減
・複数媒体を効率化し、応募単価(CPA)の低減が可能
・必要な期間だけ利用でき、柔軟な投資ができる
2. スピード向上
・専任チームが即日・大量に運用できるためスピーディー
・応募者への初期レスポンスが早まり、志望度低下を防止
・社内は面接・意思決定に集中でき、選考全体も加速
3. ノウハウ活用
・専門知見により採用活動の精度と再現性が高まる
・外注会社の最新事例やデータベンチマークを活用できる
・自社では気づきにくい改善点を提案してもらえる
これらのメリットにより、外注は単なる“業務代行”ではなく、採用力を底上げするパートナーシップとして活用できるのです。
外注活用に潜むリスク(情報共有不足・属人化の懸念)
外注には大きなメリットがある一方で、注意すべきリスクも存在します。特に多いのが「情報共有不足」と「属人化」の2点です。
情報共有不足のリスク
・外注先との連携が不十分だと、自社の採用方針やカルチャーが候補者に正しく伝わらない
・応募者対応の温度感にズレが生じ、候補者体験(CX)の低下につながる
・データの報告が遅れることで、改善のスピードが落ちる
属人化のリスク
・特定の外注担当者に依存すると、交代や契約終了時にノウハウが失われる
・自社内に採用ノウハウが蓄積されず、長期的に弱体化する恐れがある
・「丸投げ体制」になってしまうと、採用戦略の方向性自体が外部主導になりかねない
これらを防ぐためには、定期的な打ち合わせやレポート共有を徹底し、外注先をパートナーとして管理・協働する姿勢が重要です。
契約時には業務範囲や成果指標を明確にし、属人化を避ける仕組みを作ることも欠かせません。
【関連記事】失敗しないRPO導入法|採用代行を選ぶ前に見るべき5つの視点
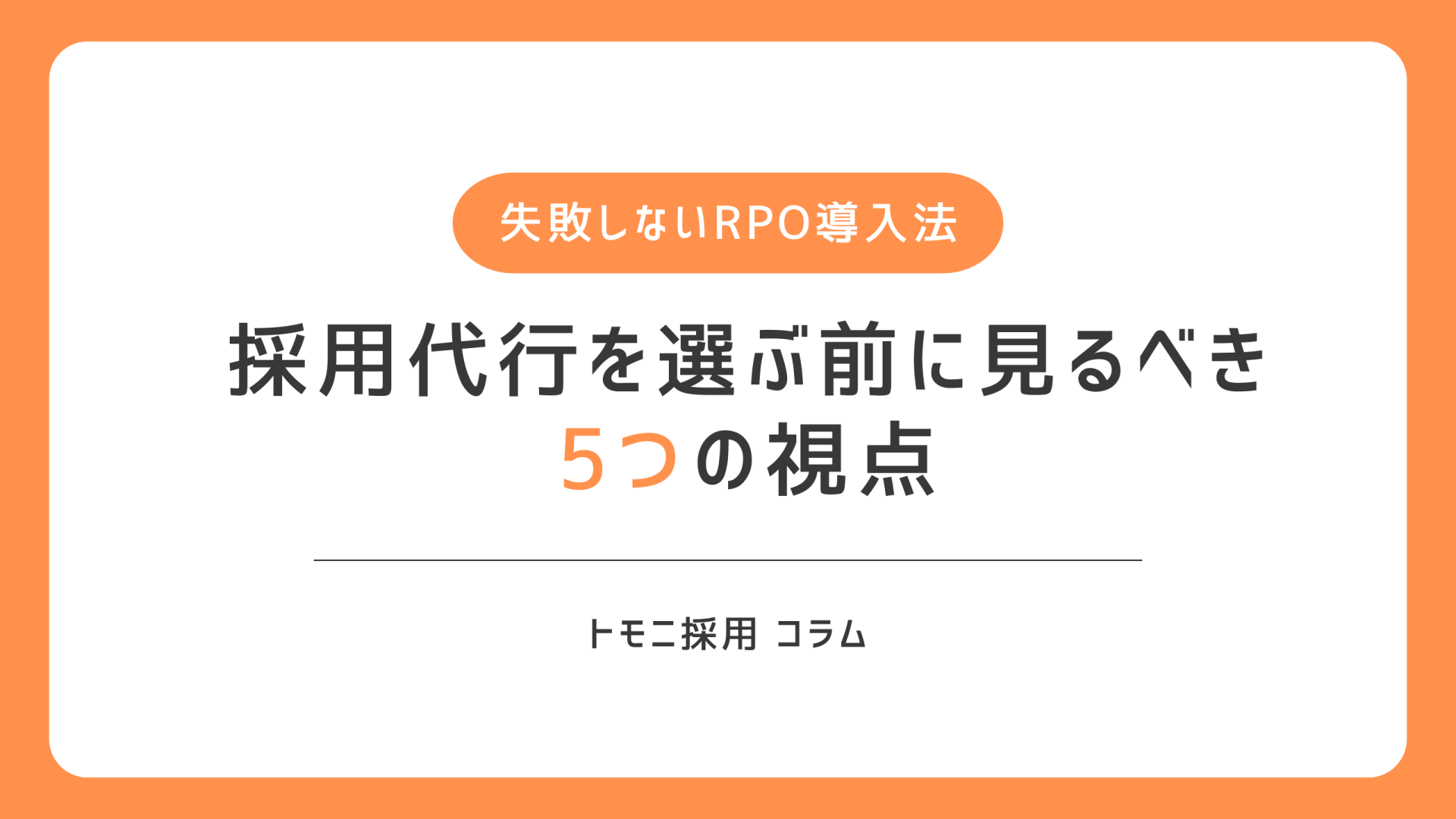
自社に合った外注先の選び方と活用のステップ
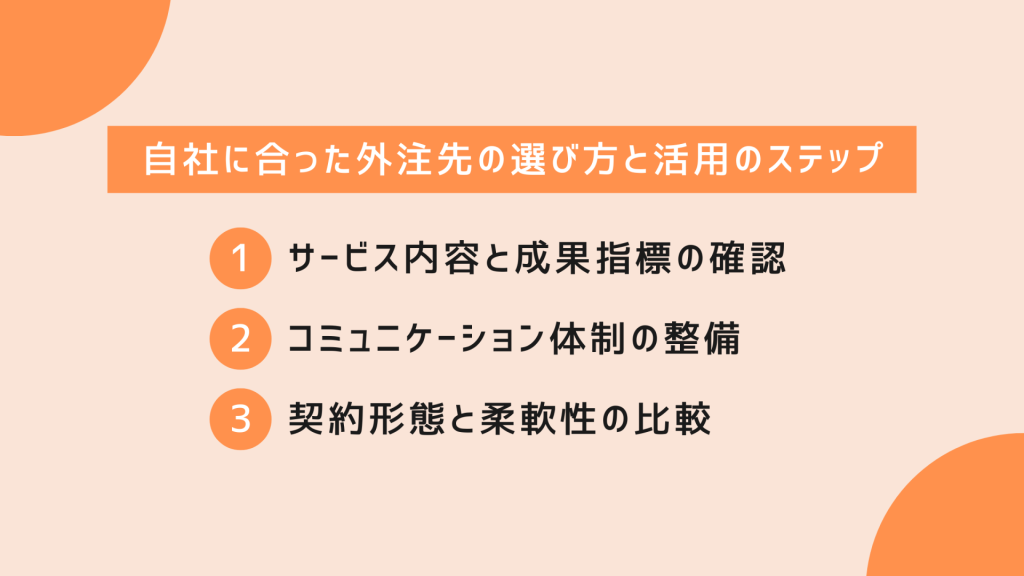
採用業務の外注は、業務効率化や成果向上につながる有効な手段ですが、すべての企業に同じやり方が当てはまるわけではありません。
外注先ごとに得意領域やサービス範囲、料金体系は大きく異なり、自社の課題や採用方針にマッチしたパートナーを選ばなければ、期待した効果を得られない可能性があります。
また、契約後の運用体制やコミュニケーションの取り方によっても成果は大きく変わります。
ここでは、自社に合った外注先を見極めるための視点と、導入から活用までのステップを整理していきます。
サービス内容と成果指標の確認
外注先を選ぶ際に最初に確認すべきポイントは、提供しているサービス内容の範囲と、設定される成果指標(KPI)です。
曖昧なまま契約してしまうと「依頼した業務がカバーされていなかった」「成果の基準が合わなかった」といったトラブルにつながりかねません。
確認すべきサービス内容
対応範囲の明確化
∟求人媒体運用、スカウト配信、応募者対応など、具体的にどこまで任せられるのかを確認
追加費用の有無
∟基本料金で対応できる内容と、オプション費用が発生する内容を整理
専門性の有無
∟IT人材に強い、若手採用に特化している、など得意領域を把握
確認すべき成果指標(KPI)
応募数・有効応募率
∟どの程度の応募や有効応募を目標とするのか
スカウト返信率
∟文面最適化やリスト精度を反映する指標
内定・入社につながる率
∟単なる母集団形成ではなく、採用成功に直結する指標を設定
成果指標が明確であれば、外注先のパフォーマンスを客観的に評価でき、自社内の改善にもつなげやすくなります。
逆に、この部分が不透明なままでは「効果があるのかどうか」が判断できず、不満や失敗につながるリスクが高まります。
コミュニケーション体制の整備
外注を活用して成果を出すには、業務の丸投げではなく、適切なコミュニケーション体制を構築することが不可欠です。
情報共有や連携が不十分だと、成果が出にくいだけでなく、自社の採用方針やカルチャーが候補者に正しく伝わらないリスクも高まります。
整備すべきコミュニケーション体制
定例ミーティングの設定
∟週次・月次での進捗確認や課題共有の場を設ける
∟成果レポートをもとに改善点をすり合わせる
連絡チャネルの明確化
∟メール、チャットツール、電話など、日常的にやり取りする手段を統一
∟緊急時の連絡フローも事前に取り決めておく
情報共有のルール化
∟候補者情報や進捗状況をリアルタイムで確認できる仕組みを整備
∟ATSや共有スプレッドシートを活用し、属人化を防ぐ
担当者の明確化
∟外注先・自社双方で責任者と窓口を明確にしておく
∟「誰に聞けば良いのか」が不明確になる状況を避ける
外注を単なる「委託先」として扱うのではなく、共通のゴールに向けて協働するパートナーとして位置づけることが大切です。
定例の打ち合わせや日常的な連絡チャネルを整えることで、迅速かつ正確な情報共有が可能になり、改善のサイクルをスピード感を持って回すことができます。
こうした体制を構築することで、外注のメリットを最大限に引き出し、採用活動全体の質を高めることができます。
契約形態と柔軟性の比較
外注を検討する際には、サービスの中身だけでなく、契約形態と柔軟性を確認することが欠かせません。採用ニーズは景気や事業計画によって変動しやすいため、契約条件が自社の状況に合っていないと、コストだけが先行してしまうリスクがあります。
契約形態でよくあるパターン:
月額固定型
・毎月一定の料金で、決まった範囲の業務を代行
・安定した支援を受けられる反面、繁忙期・閑散期の差を調整しにくい
成果報酬型
・応募数や採用数に応じて費用が発生
・成果に連動するため費用対効果を測りやすいが、短期目標に偏るリスクもある
スポット・プロジェクト型
・特定の期間や施策(例:新規事業立ち上げ時の採用強化)に限定して利用
・短期間で柔軟に導入できるが、継続的な改善サイクルは築きにくい
柔軟性を確認すべきポイント
・契約期間に縛りがないか
・業務範囲を状況に応じて拡張・縮小できるか
・契約途中での内容変更や追加オプションへの対応が可能か
特に成長企業や採用変動が大きい企業では、柔軟にカスタマイズできるサービスを選ぶことが重要です。
弊社サービスのトモニoperation(採用媒体の運用代行サービス) は、媒体運用の代行をベースにしつつ状況に合わせて支援範囲を調整いたします。支援期間内も、急な状況変化にもフレキシブルに対応も可能です。
採用媒体の運用代行サービス「トモニoperation」の詳細はこちら
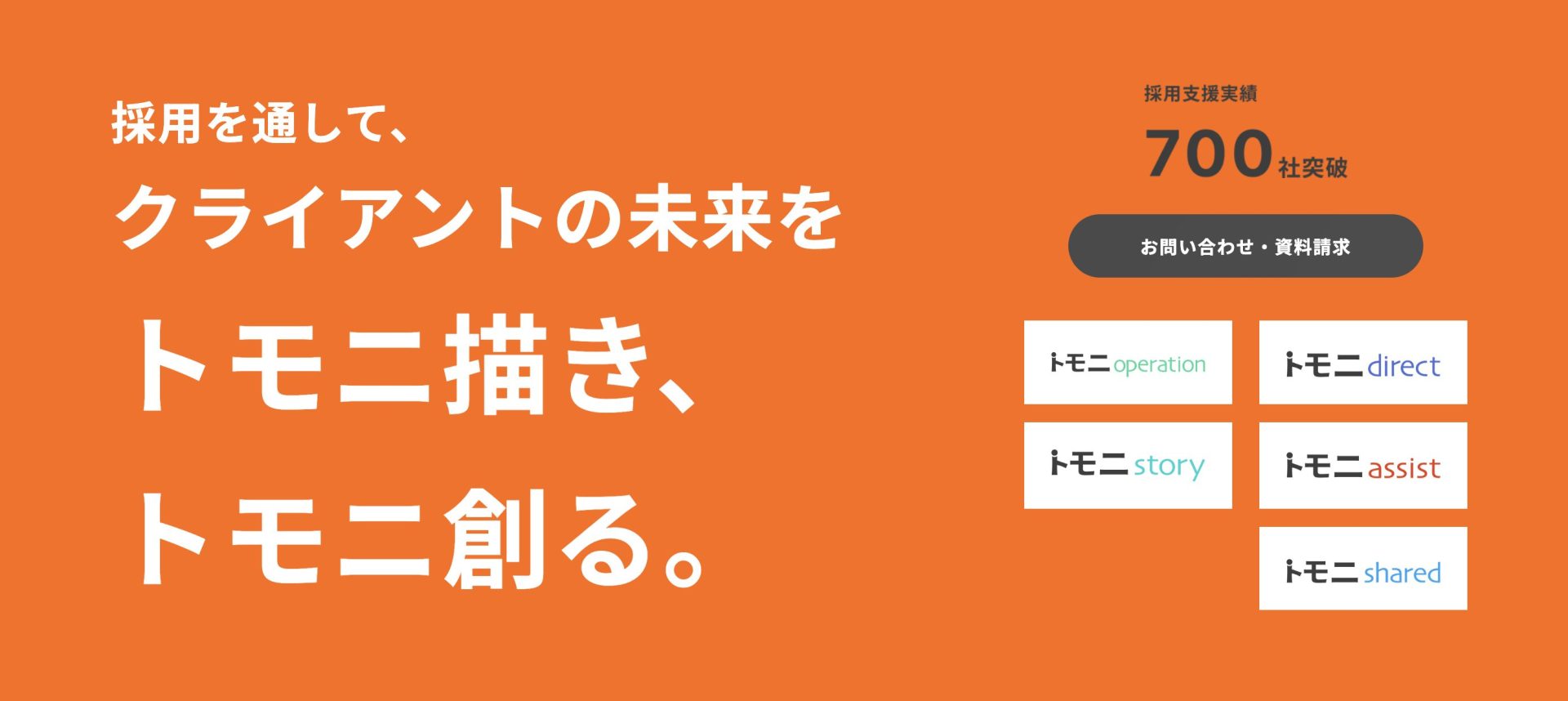
まとめ|外注で採用業務を効率化し、戦略人事に注力する
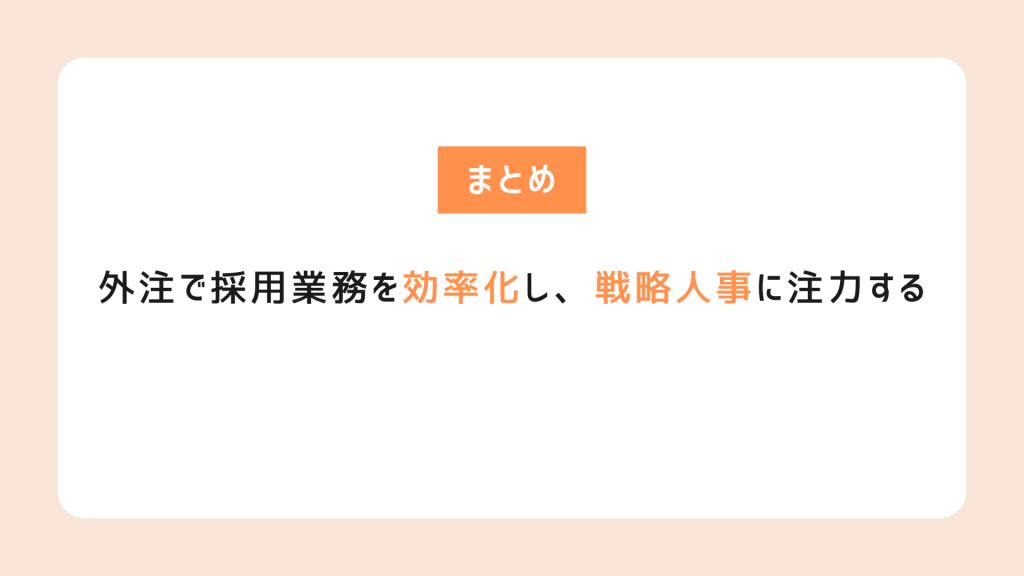
採用活動においては、求人媒体の運用やスカウト配信、応募対応など、膨大なオペレーション業務が日常的に発生します。
これらをすべて自社で担うと、人事担当者は戦略立案や候補者との関係構築といった本来注力すべき業務に十分な時間を割けなくなり、結果として採用力の低下につながりかねません。
外注を活用することで、こうした定型業務を効率的に処理し、社内リソースを「戦略人事」へ集中させることが可能になります。コスト削減やスピード向上、専門ノウハウの活用といったメリットを享受しつつも、情報共有不足や属人化といったリスクには注意が必要です。
そのためには、契約形態やサービス内容を正しく理解し、外注先をパートナーとして適切にマネジメントすることが求められます。
最終的に重要なのは、「何を外に任せ、何を自社で担うのか」という切り分けを明確にすることです。オペレーションは外注に任せ、カルチャー発信や採用判断といったコア部分は自社で行う。
このバランスを実現できれば、外注は単なる業務代行ではなく、採用活動を戦略的に進化させる手段となります。
採用リソースに課題を感じている企業は、まず自社業務を棚卸しし、外注活用の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。
【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】
株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。
私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。
「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

トモニoperationサービス資料
「トモニoperation」は、求人媒体の運用代行に特化したサービスです。
求人票の作成・更新、効果測定、改善提案など、採用担当者が負担しやすい運用業務を専門チームが代行し、応募数と有効応募率の最大化をサポートします。